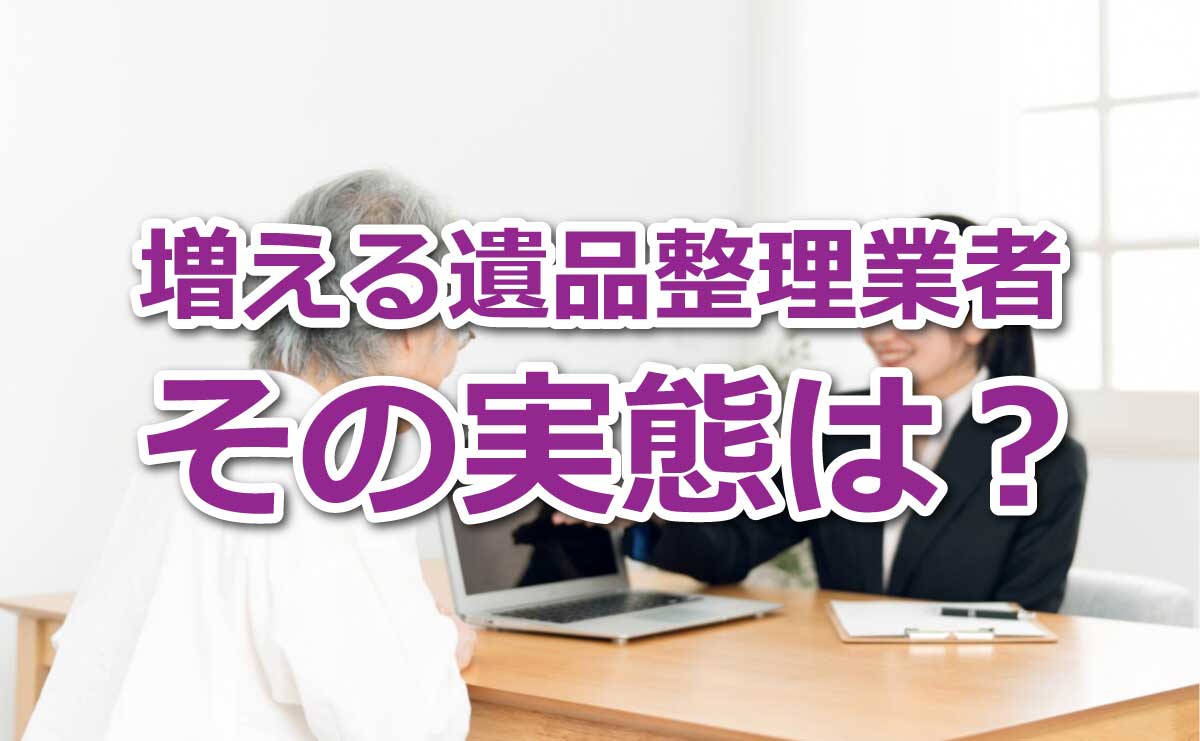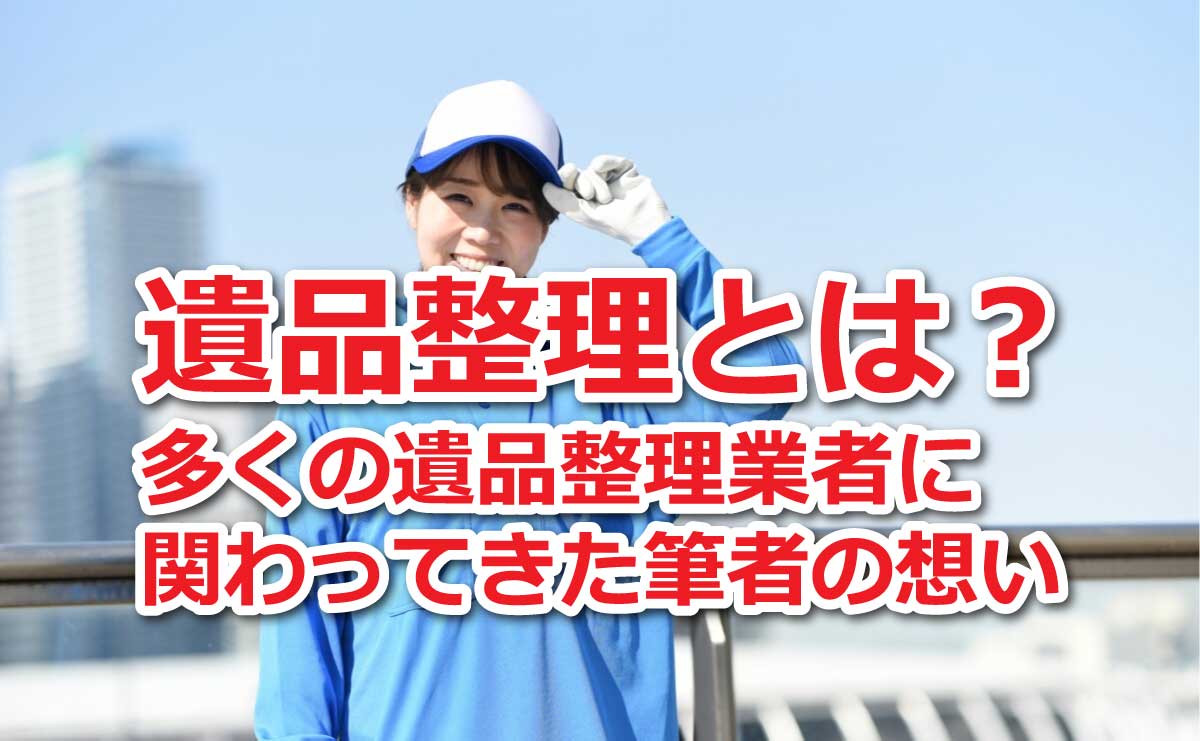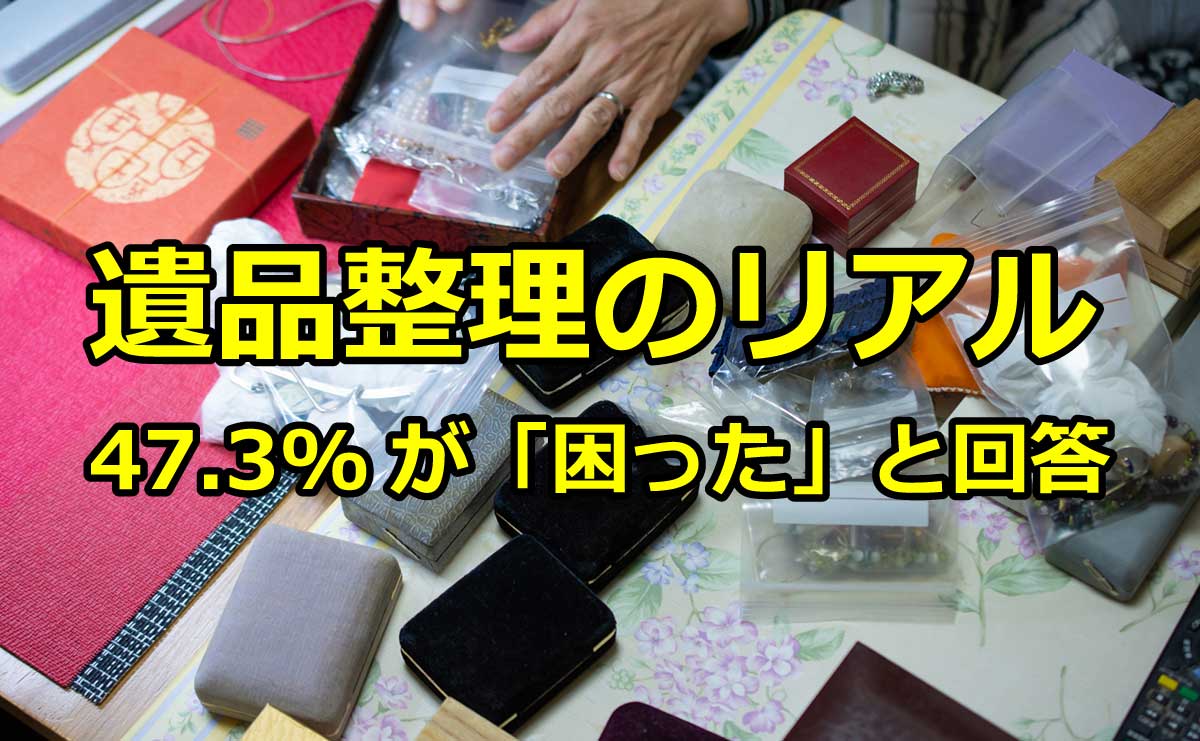
はじめに~避けて通れない「遺品整理」という現実
家族や身近な人が亡くなったとき、残された私たちが向き合わなければならないのが「遺品整理」です。感情の整理がつかない中で、生活用品や思い出の品々を前にして判断を迫られる作業は、想像以上に大きな負担となります。
株式会社NEXERと株式会社メモリードが行った調査では、遺品整理を経験した人のうち、実に47.3%が「困ったことや処分するか迷ったものがあった」と回答しています。この記事では、その調査結果をもとに、現代の遺品整理の実態や課題、そして私たちが今できる備えについて、深く掘り下げていきます。
遺品整理のタイミング~「心の準備」が整うまで待つ人が多数
遺品整理は、故人との別れを象徴する重要なプロセスでありながら、精神的にも肉体的にも大きな負担を伴う作業です。今回の調査結果によると、遺品整理を行ったタイミングで最も多かったのは「四十九日が過ぎた後(1~2か月以内)」で、全体の28.6%を占めていました。これは、葬儀直後には到底手が付けられなかったという実情を反映しているといえるでしょう。
実際、葬儀から日が浅い時期は、喪失感や悲しみの感情がまだ強く残っており、片付けどころではないという人が多くいます。葬儀の準備や関係各所への連絡、役所への届け出、相続関係の書類作成など、やるべきことは山ほどある中で、遺品整理まで手が回らないというのが現実です。
また、「まだ気持ちの整理がつかない」「物に触れるのがつらい」という声も多く、無理に急いで片付けようとすると、かえって心に傷を残してしまう可能性もあります。そのため、四十九日法要をひとつの節目とし、それが終わってから、ようやく心の準備が整って少しずつ遺品に向き合う人が多いのです。
このような背景からもわかるように、遺品整理は単なる「片付け作業」ではなく、故人と自分自身の関係を見つめ直し、心に区切りをつけるための大切な時間でもあります。たとえそれが1か月後でも3か月後でも、無理のないタイミングで始めることが、精神的な負担を減らす一つのポイントになるのではないでしょうか。
さらに、家族や親族との時間の調整も重要です。遠方に住んでいる親族が多い場合は、日程を合わせるのに時間がかかることもあります。「一人ではできない」「誰かと一緒に片付けたい」という心理的な支えも求められる場面です。
つまり、遺品整理のタイミングには正解があるわけではなく、それぞれの家庭や心情に応じた「ちょうどいい時期」があるということ。無理に急がず、焦らず、自分や家族にとって納得のいくタイミングで始めることが、心のケアにもつながります。
「自分たちで遺品整理」が主流、でも遺品整理業者の必要性を実感する人も
遺品整理の方法として、調査では「自分たちで整理した」と回答した人が大多数を占めていました。その割合は91.3%にも上り、家族や親族が力を合わせて故人の遺品に向き合う姿が、今なお一般的であることが分かります。
その背景には、「時間をかけてゆっくり整理したかった」「故人の物に一つひとつ触れながら、思い出を辿りたかった」といった心情的な理由があります。遺品整理は単なる片付けではなく、故人との対話のような側面もあるため、自分の手で丁寧に行いたいという思いが強いようです。また、「業者に頼むと高額になりそうで不安」「自宅に他人を入れることに抵抗がある」「プライベートなものを他人に見せたくない」といった、金銭的・心理的な壁も多くの人が挙げていました。
特に、アルバムや手紙、日記帳、衣類など、故人の人格や歴史を感じさせる品々に触れる際には、「自分で整理したい」「時間をかけて選別したい」という気持ちが自然と湧いてくるのも無理はありません。こうしたプロセスが、遺された人たちの心の整理にもつながっていくため、ゆっくりとしたペースで進めたいという思いが反映されているのでしょう。
- 時間をかけてゆっくり整理したかった
- 業者に頼むのは金銭的な負担が大きい
- 他人に見せたくないものがある
一方で、「業者に依頼した」と回答した人は8.7%にとどまりましたが、その多くが「物の量が多すぎて自分たちだけでは無理だった」「特殊清掃や大量のゴミ処理、家電の廃棄など専門性が必要だった」といった理由を挙げており、業者の力を借りる必要性を実感した人たちの切実な声が浮かび上がっています。
とくに一人暮らしだった故人の住まいが丸ごと遺されているケースや、ゴミ屋敷に近い状態であった場合、素人だけではどうにもならないのが現実です。粗大ゴミの搬出、リサイクル家電の回収、建物の解体前清掃など、法律や手続きも関わる部分については、やはり専門業者のノウハウが求められます。また、孤独死などで特殊清掃が必要な現場では、消臭・除菌作業を含むプロの介入なしでは安全性が確保できないこともあります。
実際に業者に依頼した人からは、「短時間で片付いて助かった」「物理的にも精神的にも救われた」「供養の相談にも乗ってもらえた」など、感謝の声も多く寄せられています。費用はかかるものの、負担を軽減できるメリットは大きく、今後はこうしたサービスを選択肢に入れる人がますます増えていくと予想されます。
また、最近では「遺品整理士」などの専門資格を持ったスタッフが在籍する業者や、「女性スタッフのみで対応」「仏壇の供養も可能」など、利用者のニーズに合わせたサービス展開をしている業者も増えています。インターネットや口コミで比較検討しながら、信頼できる業者を見つけることも重要です。
つまり、「自分たちで行う」ことにも「業者に頼る」ことにも、それぞれに意味と価値があります。大切なのは、無理をしないこと。そして、どちらを選ぶにせよ、「故人への思いやり」と「残された人の心の安定」の両立を意識した判断をすることが、後悔のない遺品整理につながるのではないでしょうか。
処分に迷う品々~神仏・写真・故人のこだわりの品…
遺品整理の過程で、もっとも多くの人が頭を悩ませるのが「処分してよいのか分からない物」との向き合い方です。今回の調査では、47.3%もの人が「遺品整理で困ったことがあった」と答えました。その理由の多くが、“捨てる・残す”という判断を迫られたときの、感情面での葛藤です。
特に処分に迷ったものとして挙げられていたのが、神棚や仏壇、数珠、位牌などの宗教・信仰に関わる品々です。これらは「単なる物」ではなく、「魂が宿っている」「故人の祈りが込められている」と考える人も多く、ゴミとして処分することに大きな罪悪感を抱く人が少なくありません。
一方で、保管しておくにしてもスペースの問題があったり、次の世代が信仰を引き継がない場合、誰が責任を持つべきかという悩みもあります。寺院や供養専門の業者に相談するケースもありますが、費用が発生するため、気軽に依頼できないという声もあります。
また、写真やアルバム、手紙といった“思い出の品”も非常に多くの人が迷うジャンルです。故人の若い頃の写真、家族旅行の記録、感謝の気持ちが綴られた手紙など、見れば見るほど捨てられなくなってしまうというのが多くの人の実感です。
たとえ何十年も前の品であっても、それを目にした瞬間に当時の情景や気持ちがよみがえり、「処分する」という行為が“思い出を消すこと”のように感じられてしまうのです。そのため、なかなか作業が進まず、整理が長引いてしまうこともしばしばあります。
さらに、遺族では使わないけれども、故人が大切にしていたブランド品や趣味のコレクションなども、判断に迷う代表格です。例えば、高級腕時計、万年筆、絵画、カメラ、着物、茶道具、CD・レコード、ゴルフ道具など、故人が愛着を持っていた物には、本人の“生き方”や“こだわり”がにじみ出ています。
「自分は使わないけれど、故人の大切な宝物だから捨てたくない」「リサイクルショップで売るのも心苦しい」「誰か使ってくれる人がいれば…」といった気持ちの揺れが強く、結局手を付けられずに箱にしまい込んでいる家庭も少なくないのです。
このように、遺品整理の本質的な難しさは「物の量」ではなく、「物に宿った記憶や思い出との距離感」にあります。物理的には簡単に処分できるものであっても、それに込められた想いや故人とのつながりが深いほど、その決断は重くなります。
最近では、こうした“感情の整理”をサポートするためのサービスも増えてきました。例えば、「供養の気持ちで写真や手紙を焚き上げる」「思い出の品をデジタル化して保管し、実物は処分する」「一部をアクセサリーやオブジェとしてリメイクする」といった選択肢です。
大切なのは、「残す」か「捨てる」かという二択だけでなく、“気持ちに折り合いをつけながら手放す方法”を模索すること。そのプロセスが、故人との別れに対して自分なりの納得を得るための手段となるのです。
- 神棚や仏壇などの神仏関係の品
- アルバムや思い出の手紙
- 遺族では使わないが、故人が大切にしていた品(ブランド品、コレクションなど)
生前の意思表示はわずか8.7%~なぜ少ないのか?
遺品整理をスムーズに進めるうえで鍵となるのが、故人の「生前の意思表示」です。しかし、今回の調査によると、生前に「自分の遺品についてどうしてほしいか」を家族に伝えていた人は、全体のわずか8.7%という結果でした。つまり、約9割以上の人は何の意思も残さないまま亡くなっているのが現実です。
その中でも、「全部捨てていいよ」といったシンプルな言葉だけを伝えていたケースが多く見られましたが、実際にどこまでを捨ててよいのか、何を残しておくべきかといった細かい判断を残された家族に委ねている場合がほとんどです。なかには「ほしいものがあれば自由に持っていって」と話していた人もいたようですが、それすら曖昧な表現であり、具体的な処分方法や形見分けの基準まで明示していたケースはごくわずかでした。
では、なぜこれほどまでに生前の意思表示が少ないのでしょうか。
第一の理由として考えられるのが、「死について語ることへの心理的抵抗感」です。日本では古くから、「死に関する話題は縁起でもない」「死を口にするのは不吉」という文化的な背景があり、家族や親しい人と“もしもの時”について話し合うこと自体が敬遠されがちです。「まだ早い」「まだ元気だから大丈夫」といった言葉で先延ばしにされ、気づけば何も準備されないまま最期を迎えてしまうのです。
第二の理由は、「生前整理」や「エンディングノート」への理解不足です。近年では少しずつ浸透してきたこれらの言葉ですが、まだまだ「年配の人がやるもの」「余命宣告を受けた人の話」といった誤解が根強く、若いうちから取り組むという発想にはなかなか至っていません。
また、「整理しておくべき物の範囲が分からない」「どこから手を付ければよいか分からない」といった実務的なハードルも無視できません。写真、書類、貴金属、デジタル遺品、SNSアカウント、ペットの世話、貸金庫の鍵……。遺品とは言ってもその範囲は非常に広く、意思を明確にするには時間もエネルギーもかかるため、つい後回しになってしまいがちです。
実際、遺された家族の立場からすれば、「本人の気持ちが分からないまま、こちらで全部判断しなければならない」というのは大きな負担です。「本当はこれは残しておきたかったかもしれない」「この手紙は見せるべきか迷う」など、小さなもの一つ取っても、その選択には気力と神経を使います。
それに加え、現代は単身世帯の増加や核家族化の進行により、家族間のコミュニケーションが減少しているという社会背景もあります。親と子が同居していない、連絡頻度も少ない、そういった中では、あえて遺品や死後のことについて語り合う機会をつくること自体が難しくなっているのです。
とはいえ、意思表示の重要性は年々高まっています。たとえば、エンディングノートに自分の希望を書き記しておくだけでも、遺された人の精神的負担は大きく軽減されます。また、「このアルバムだけは残してほしい」「この指輪は○○に譲りたい」といった具体的な指示があることで、形見分けにまつわる家族間のトラブルも回避しやすくなります。
今はまだ元気でも、「備え」は早いに越したことはありません。死を前向きに捉え、「人生のまとめ」として生前整理や意思表示をすることは、残された家族への“最後の思いやり”にもつながります。生きているうちに「ありがとう」と言える関係を築くこともまた、現代の終活のひとつのかたちなのかもしれません。
遺品整理における「感情」の重さ~ただの「モノ」ではない
遺品整理というと、多くの人は「家の中のものを片付ける作業」として、物理的な行為をイメージするかもしれません。しかし、実際に経験した人の多くが口を揃えて言うのは、「これは片付けではなく、感情との向き合いだった」ということです。
遺品は、ただの「物」ではありません。その一つひとつに、故人の人生の断片や思い出、家族との関係、日々の暮らしの痕跡が詰まっており、残された人にとっては非常に“重たい存在”になります。
たとえば、故人がいつも使っていた湯呑みや、枕元に置いていた目覚まし時計、書きかけの手帳など、日用品のひとつひとつに「そこに生きていた証」が刻まれているように感じられます。そのため、たとえ古びた物であっても、処分しようとした瞬間に胸が詰まり、手が止まってしまう――そんな体験をした人は少なくありません。
実際、以下のような声が多く寄せられています
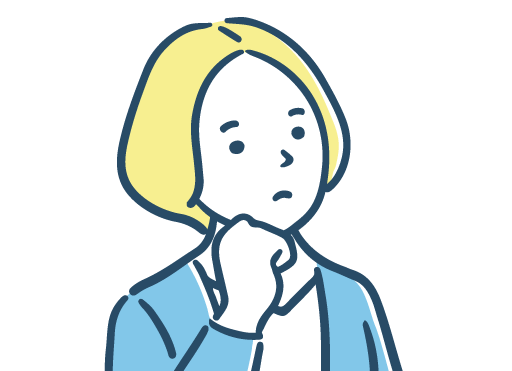
故人が愛用していた日用品でも、見るたびに涙が出る。捨てようと思っても、手が震えてしまって…



手紙や写真は捨てるに捨てられず、今も押し入れの奥にしまったまま。見る勇気も、捨てる覚悟も持てない…



自分だけでは判断できなくて、兄弟で何時間も話し合った。結局、誰も処分の決断ができなかった…
こうした声からも分かるように、遺品整理とは「物の整理」ではなく、「感情の整理」でもあります。多くの人にとって、遺品整理の時間は、ただの清掃作業ではなく、「故人との最期の対話」であり、「静かな別れの儀式」となっているのです。
また、家族や兄弟など、複数人で整理を行う場合、思い出の重さが人によって違うことが、さらに判断を難しくします。ある人にとっては思い出深いぬいぐるみも、別の人にとっては記憶にない単なる古い物に過ぎない。こうした温度差が、時には小さな衝突やすれ違いを生むこともあります。
さらに、「誰かが残した方がいいのではないか」「もらってもらったほうが、供養になるのでは」といった“気遣い”も絡まり、整理の作業は思っている以上に進みません。「処分しよう」と頭では分かっていても、感情が追いつかず、何年もそのまま保管されている遺品も珍しくないのです。
こうした背景を踏まえると、遺品整理においてもっとも大切なのは、“焦らないこと”です。時間をかけて、心が整理されるまで待つ。それが、故人への敬意であり、遺された自分たちへの思いやりでもあります。
また、最近では「想いの整理」に寄り添う形で、遺品の一部をメモリアルアクセサリーに加工したり、写真をアルバムにまとめて「故人の記録」を作るといったサービスも増えています。すべてを手放すのではなく、一部を形として残しながら心に折り合いをつける――そうした方法も、感情に寄り添った遺品整理の一つのかたちです。
つまり、遺品整理は単なる作業ではありません。それは、故人の人生に「ありがとう」と言うための時間であり、自分自身が前を向くための大切な通過儀礼なのです。
専門家に聞く~遺品整理業者に頼むメリットと注意点
遺品整理というのは、想像以上に労力と時間、そして精神的エネルギーを必要とする作業です。とくに故人の住まいが一軒家であったり、荷物の量が多い場合は、家族だけで対応するのが難しいケースも多く、そういったときに頼りになるのが「遺品整理業者」です。
実際に業者に依頼した人からは、次のような肯定的な声が多く寄せられています。
- 「仕分けから処分まで手際よくやってくれた。こちらはほとんど立ち会うだけで済んだ」
- 「高齢の自分たちでは絶対に無理だったので、本当に助かった」
- 「仏壇や写真などの供養もしてくれて、心の整理までできた気がする」
- 「家財を処分しながら、価値のあるものは買い取ってくれて、費用の足しになった」
このように、プロの手による整理は物理的な負担だけでなく、精神的なストレスをも軽減してくれる存在です。特に、孤独死やゴミ屋敷化した現場など、通常の清掃では対応しきれないケースでは、業者の専門的なノウハウが不可欠です。特殊清掃や消臭、消毒、害虫駆除など、一般家庭では難しい工程もすべて対応してくれるのは大きな魅力でしょう。
一方で、すべての業者が信頼できるわけではありません。依頼者の無知や弱みにつけ込むような悪質業者の存在も指摘されており、以下のようなトラブルの報告も少なくありません。
- 「料金が高すぎた。見積もりでは10万円と聞いていたのに、作業後に20万円を請求された」
- 「事前説明と実際の作業内容が大きく異なっていた。『供養する』と言っていた遺品が、実は処分されていた」
- 「不用品を不法投棄されたと近所から通報があり、こちらが責任を問われかけた」
こうしたトラブルを避けるためには、業者選びの段階での情報収集が非常に重要です。具体的には以下のようなポイントを意識するとよいでしょう。
遺品整理士が在籍しているか
「遺品整理士」は、一般社団法人「遺品整理士認定協会」が認定する資格です。遺族の心情への配慮や適正な処分、供養の知識など、専門的な研修を受けていることが証明されるため、一定の安心材料となります。
見積もりは複数社から取得する
料金体系が不透明な業者もあるため、必ず複数の業者に見積もりを依頼し、内容を比較検討することが大切です。「作業一式」で料金を提示する業者よりも、「何にいくらかかるか」を明示してくれる業者のほうが信頼できます。
サービス内容を契約前に明確に確認
「供養の可否」「リサイクル対応」「処分方法の透明性」など、気になる点は事前に細かく確認しましょう。契約書や作業内容の明細があるかどうかも、信頼性のバロメーターです。
口コミ・評判・トラブル報告を事前にチェック
ネット上の口コミや評判、消費者センターや国民生活センターへの苦情件数なども参考にして、リスクを事前に回避しましょう。会社の公式サイトだけでなく、第三者のレビューも確認すると効果的です。
遺族とのコミュニケーションを大切にしてくれるか
遺品整理は単なる作業ではなく、家族にとっての“心の区切り”の時間でもあります。そうした想いを理解し、こちらの話をしっかり聞いてくれる担当者がいるかどうかも、重要なポイントです。
遺品整理業者に依頼することは、決して「楽をする」ためではありません。むしろ、限られた時間や体力の中で、より丁寧に故人と向き合うための手段でもあります。
ただし、業者に「全部任せきり」にするのではなく、自分たちで確認したい部分・思い出を整理したい品については、あらかじめ伝えておくことも大切です。「ここは自分たちでやりたい」「この品は残したい」といった希望があれば、しっかりと共有しましょう。
信頼できる業者との連携によって、遺品整理は単なる片付けではなく、「感謝」と「旅立ち」の儀式となり、心の負担を少しでも軽くすることができるのです。
これからの課題~デジタル遺品・孤独死・空き家問題とどう向き合うか
遺品整理というテーマは、単に「亡くなった人の持ち物を整理する」という従来のイメージを超え、今や多くの社会的課題と深く結びついています。中でも、「デジタル遺品」「孤独死」「空き家問題」は、これからの時代に避けて通れない大きなテーマとなりつつあります。
デジタル遺品の取り扱い・見えない財産、残されたままにしないために
私たちの生活の中で、スマートフォンやパソコンは欠かせない存在となっています。写真、動画、連絡先、SNSのメッセージ、メール、ネットバンキング、暗号資産、サブスクリプション契約など、日常のあらゆる情報がデジタルの中に詰め込まれています。
しかし、故人の死後、これらのデータにアクセスする手段がないまま、スマートフォンやパソコンが「デジタル金庫」と化してしまうケースが後を絶ちません。ロックが解除できない、パスワードが分からない、どのクラウドサービスを使っていたのかも不明――。こうなると、遺族は重要な情報に一切アクセスできず、遺産の相続や契約の解約、未払い料金の発生、写真などの思い出の喪失といった事態に直面することになります。
こうしたトラブルを防ぐには、「デジタル遺言」「デジタル資産リスト」の作成が効果的です。たとえば、パスワード管理アプリにアクセス情報をまとめ、信頼できる家族にパスコードを伝えておく。あるいは、エンディングノートに利用サービスや契約情報を書き残す。これらの一手間が、残された家族の負担を大きく軽減します。
孤独死という現実・誰にも看取られずに亡くなることの影響
高齢化社会と単身世帯の増加により、近年増えているのが「孤独死」です。誰にも気づかれずに自宅で亡くなり、数日後~数週間後にようやく発見されるケースは、都市部を中心に深刻化しています。
こうした現場では、死後の時間の経過により、遺体の腐敗・異臭・害虫発生などが起こり、通常の遺品整理だけでなく、特殊清掃やリフォーム、近隣への対応も必要になります。精神的にも、身体的にも、そして経済的にも、遺族にとっては大きな負担です。
また、孤独死した方の多くは身寄りがない、あるいは家族との交流が少ないため、誰が遺品を整理するのか、どこに連絡すればいいのかが明確でなく、自治体や管理会社が対応に苦慮することも珍しくありません。
これに対応するため、地域コミュニティでの見守り体制の強化、自治体による「終活支援」「身元保証制度」、民間企業による「死後事務委任契約サービス」などが注目されています。また、孤独死の現場に対応できる専門の清掃・整理業者の育成も急務です。
空き家問題と遺品の放置・誰が処理するのか、どこまで責任を持てるのか
空き家問題も、遺品整理と密接に関係しています。親が亡くなり、実家が空き家となったまま放置される。誰も住む予定がない、土地建物の相続登記が進まない、固定資産税だけが毎年かかる…。こういったケースは全国で増え続けています。
空き家の中には故人の遺品がそのまま残されていることも多く、建物の老朽化とともに不法侵入や火災のリスクが高まります。近隣住民とのトラブルにも発展しかねません。誰が片付けるのか、どう処分するのか、費用は誰が出すのか――法的な問題も含め、判断が難しい状況に陥るケースが後を絶ちません。
この問題に対し、2023年には改正空家対策特別措置法が施行され、放置された空き家に対する行政の関与が強化されました。自治体は「管理不全空家」に対して改善命令や代執行を行うことができ、場合によっては強制的に取り壊すことも可能になります。しかし、その過程で生じる遺品の処理については、引き続き家族や相続人の責任となるため、早期の整理・対応が求められます。
地域・行政・民間が連携する時代へ
このように、現代の遺品整理は「家族だけの問題」では済まされなくなっています。孤独死や空き家がもたらす社会的影響、デジタル遺品による混乱など、さまざまな領域に波及するからこそ、今後は「地域」「行政」「民間業者」が連携した体制の整備が必要不可欠です。
具体的には、
- 地域内での情報共有や見守り活動
- 行政による相談窓口やガイドライン整備
- 民間業者によるワンストップサービスの提供(遺品整理・供養・不動産処理・デジタル対応など)
など、多方面からの支援体制を充実させることが、これからの課題解決の鍵となります。
遺品整理は、人生の終わりにおける「最後の片付け」であり、社会が向き合うべき“未来の現実”でもあります。一人ひとりの意識と、社会全体の仕組みづくり、その両方が求められる時代になってきているのです。
おわりに~備えることが、残される人への最大の思いやり
遺品整理は、ただ物を片付けるだけの作業ではありません。故人が遺したモノを通じて、思い出と向き合い、別れの現実を受け入れる――それは、残された人々にとって非常に重く、そして繊細な時間です。その負担は、精神的なものだけではなく、時間的・体力的、さらには経済的なものにも及びます。
だからこそ、私たちが「自分が死んだ後のこと」に少しずつでも備えておくことは、残された家族への最大の思いやりになるのです。
たとえば、エンディングノートに自分の気持ちや希望を記しておくこと。形見分けを希望する品や、捨ててもらって構わないもの、供養をお願いしたいものなどをあらかじめ明示しておけば、遺された人々は「これは捨てていいのか」「誰かに譲った方がよいのか」といった迷いから解放されます。
また、銀行口座や保険、サブスクリプション契約、各種IDやパスワード、借りている物件やローンの有無など、日常生活で蓄積された“情報”を整理して伝えておくことも大切です。特に、デジタル遺品の管理については、今後ますます重要性を増す分野です。
準備というと、「まだ早い」「縁起でもない」と敬遠する気持ちも分かります。しかし、備えることは「死を受け入れること」ではなく、「生きている今を大切にするための行動」です。将来、家族が困らないように、自分自身が納得した人生の終わり方を選ぶこと。それが“生き方”のひとつとして、自然に受け入れられる世の中になっていけばと願います。
そして何より、備えることで、自分自身の心にも安心が生まれます。「これだけ伝えておけば大丈夫」「自分の思いはちゃんと残せた」という安堵は、終活という言葉のイメージ以上に、日常の暮らしに穏やかさをもたらしてくれるはずです。
いつか必ずやってくるその日のために、少しずつ、自分なりの準備を始めてみませんか。それは決して“死に向かう行為”ではなく、“大切な人を想う行為”であり、“自分の生き方を見つめ直す時間”でもあるのです。