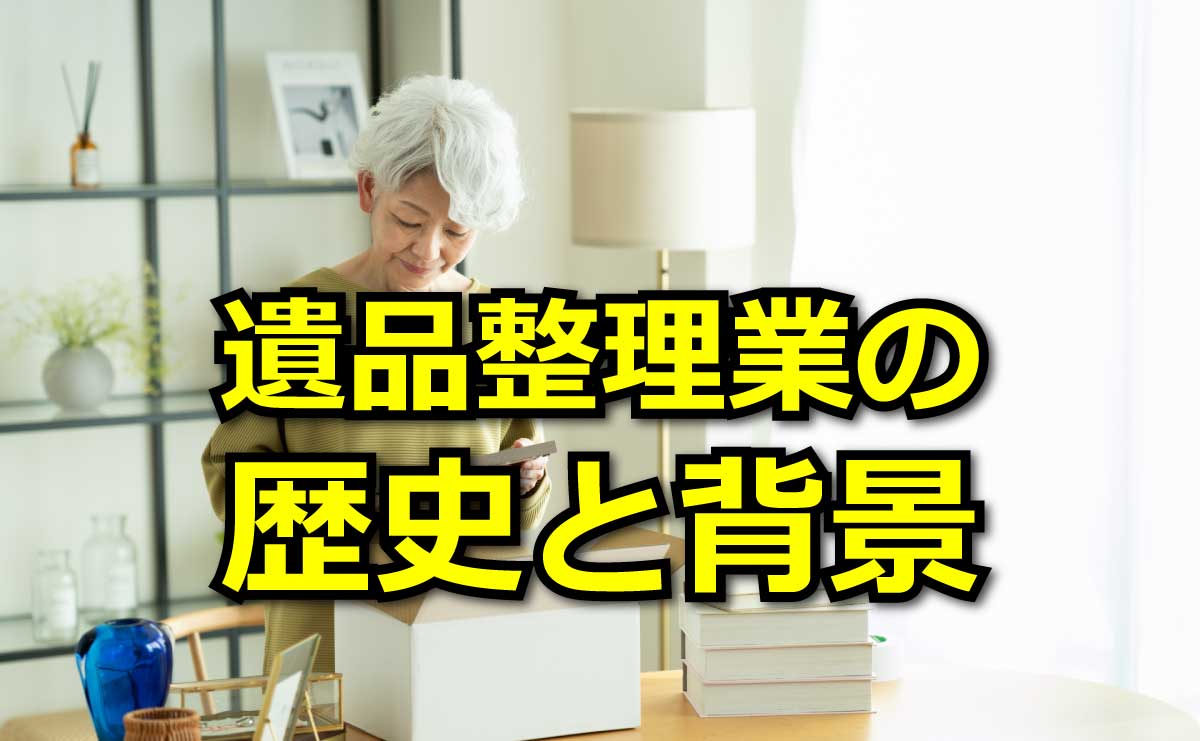中国新聞の電子版に以下のような記事を見かけました。記事を引用します。
広島市に住む50代男性が、急逝した義母の家を整理するため不要品の訪問買い取り業者を呼んだところ、業者が「貴金属はないか」としつこく尋ね、遺品の指輪を契約書なしに勝手に持ち出すというトラブルに遭遇した。後に返却されたが、当初のたんす処分費も相場の1.5倍と判明。男性は「たんすではなく貴金属狙いだった」と怒りをあらわにしている。
こうした訪問買い取りサービスは、終活や遺品整理の需要を背景に新型コロナ以降拡大しているが、トラブルも増加傾向にある。遺品整理士認定協会によれば、一部には悪質な業者もおり、「押し買い」的な手法が形を変えて続いているという。
訪問買い取りは2013年にアポなし訪問が禁止されたが、「たんすや着物の買い取り」として依頼を受け、当日になって貴金属を求める手法は法律のグレーゾーン。国民生活センターによると、買い取りサービスに関する相談は2015年度の90件から2024年度は速報で204件と増加し、解約時の高額なキャンセル料の請求など深刻なケースも多い。
専門家は「おかしいと思ったらすぐ消費生活センターに相談を」と呼びかけている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4075367c9fa186c58bbf55e441565d5717bcd9b6
「ちょっと片づけを手伝ってもらうだけのつもりだったのに、気づいたら大切な指輪がなくなっていた」
家族を見送ったあとの住まいには、思い出とともにたくさんの家財が残ります。そんなとき、家具や着物を引き取ってくれる「訪問買い取りサービス」は、とても便利に見えるかもしれません。ですが、いま全国でその裏側にあるトラブルが増えているのをご存じでしょうか?
遺品や不要品の整理を口実にして貴金属を狙ったり、強引な契約を迫ったり、場合によっては家族の大切な思い出が勝手に持ち去られてしまうケースまで報告されています。
このコラムでは、実際に寄せられた声や事例をもとに、訪問買い取りサービスの現状と注意点、そしてどうすれば安心して利用できるのかを、わかりやすくお伝えしていきます。大切な人の遺品だからこそ、安心して整理したい…そんなあなたに、知っておいてほしい情報をまとめました。
はじめに
「遺品の指輪が勝手に持ち出された」訪問買い取りの落とし穴
「母の遺品である指輪を、売るつもりなどなかったのに業者が勝手に持ち出した」。そんな憤りの声が、中国地方の自治体職員の男性から新聞社に寄せられました。彼は義母の急逝を受けて家を相続し、家財整理の一環で訪問買い取り業者を呼んだところ、古いたんすには目もくれず、「貴金属があれば処分費を安くできる」と持ちかけられました。妻が一時的に見せた指輪を、契約書も交わさず「預かる」として持ち帰られたのです。冷静になった夫婦が抗議した結果、数時間後に返却されましたが、最初に提示された処分費は相場より5割も高く、結果的にこの業者は信用できない存在であったと気づかされたといいます。このような「貴金属狙い」の事例は決して珍しくなく、誰もが被害に遭う可能性がある身近な問題です。
終活ブームとコロナ禍が加速させた「訪問買い取り」
新型コロナウイルスの感染拡大以降、自宅で過ごす時間が増えたことに加え、高齢化社会の進展や「終活」への関心の高まりを背景に、訪問買い取りサービスの需要が急拡大しました。「古家具や着物を高価買取」「片付けを丸ごとサポート」といった謳い文句でインターネット広告やSNSに現れる業者が増え、気軽に利用を始める人も多くなっています。しかしその一方で、名目上は不要品の買い取りでも、実際には貴金属など高価なものを狙う悪質業者の存在が目立つようになりました。国民生活センターによれば、関連する相談件数はこの10年で2倍以上に増加。高齢の親世代に代わって手続きを進める子世代がトラブルに巻き込まれるケースも目立っています。訪問買い取りは、今や慎重な対応が求められる「リスク付きのサービス」になっているのです。