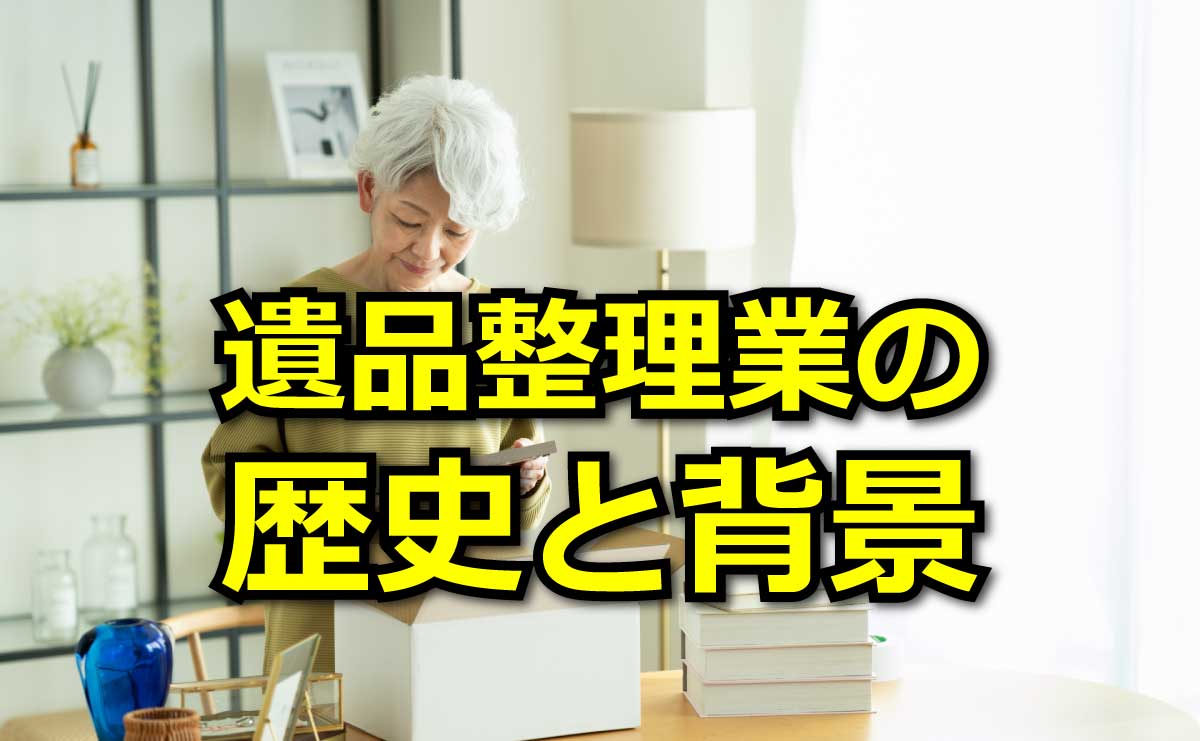かつて遺品整理は、家族や親族が集まり、故人を偲びながら行うのが一般的でした。しかし現代では、少子高齢化や核家族化の進行によって「身内だけで片付けることが難しい」状況が増えています。遠方に住んでいる、仕事や家庭の事情で時間を確保できない、高齢で体力的に対応できないといった理由から、専門業者に依頼するケースが年々増加しています。
その一方で、遺品整理をめぐるトラブルも社会問題となっています。不法投棄や高額請求、許可を持たない業者による違法な処理など、遺族の負担や心情を踏みにじる事例も少なくありません。大切な思い出の品や財産が関わるからこそ、適切な知識と倫理観を持つ人材の存在が求められています。こうした背景から、遺品整理を正しく導き、遺族に寄り添う「遺品整理士」という専門資格が注目を集めるようになったのです。
遺品整理士資格の歴史と実績
遺品整理士養成講座を開講。「遺品整理士」という名称の資格制度が誕生。
初年度から受講者が全国に広がり、認定者数が増加。業界における認知度が徐々に高まる。
会員数が数千人規模に拡大。孤立死や高齢化の進行を背景に、マスメディアで遺品整理の必要性が取り上げられる。
法人会員制度が整備され、葬儀社・不動産会社・清掃業者など多業種と連携。資格の社会的信用度が向上。
会員数が 5万人を突破。業界団体として全国的に確立した地位を得る。コロナ禍で孤独死・空き家整理の需要が急増。
資格制度発足から10年を迎える。記念シンポジウムや啓発活動が展開され、社会インフラとしての意義を再確認。
法人会員が 1,500社を突破。行政やメディアとの連携が進み、業界全体の健全化が加速。
会員数 6万人を超える。資格取得者は全国に広がり、地域ごとの支援活動にも発展。
開講から15周年を迎える節目の年。法人会員は1,600社以上に達し、遺品整理士は業界標準資格として定着。