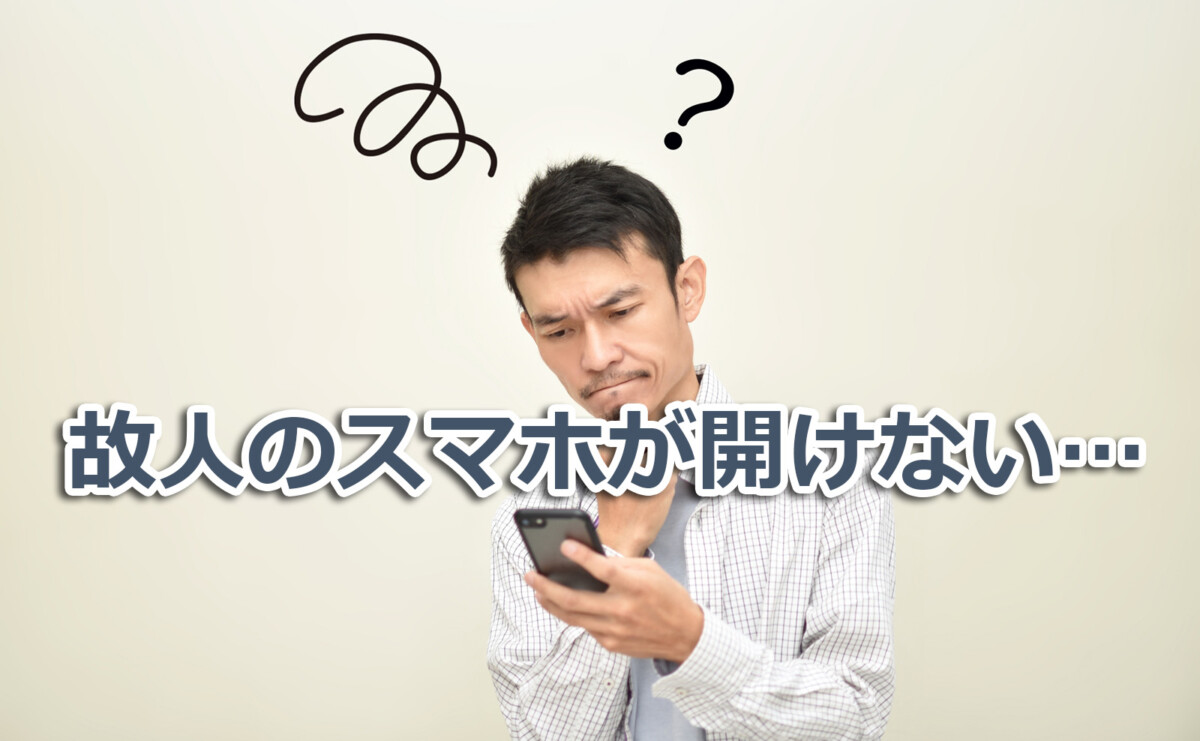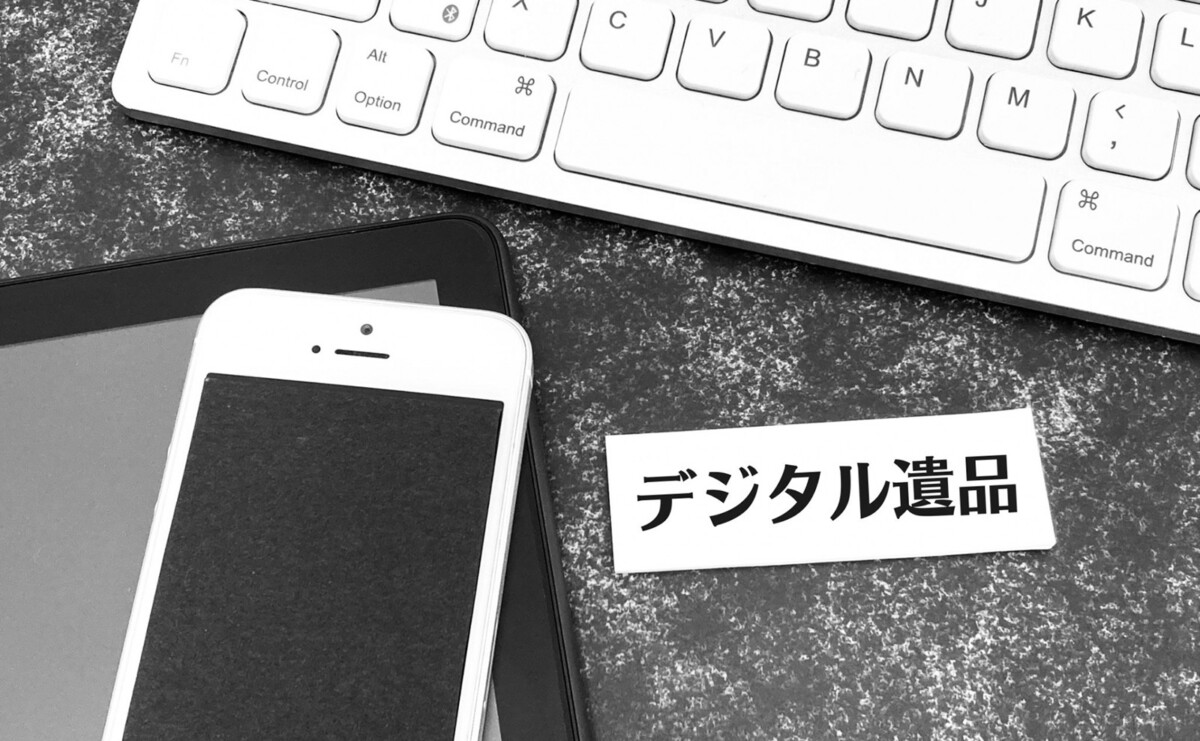SNSの追悼アカウントとは?
SNSの普及に伴い、各サービスは「追悼アカウント」という仕組みを整備するようになりました。代表的なものにFacebookやInstagramがあり、一部はLINEなどでも対応が見られます。追悼アカウントとは、故人のアカウントを削除せずに残し、家族や友人がその人を偲ぶ場として利用できるようにした制度です。
たとえばFacebookでは、生前に「追悼管理人」を指定でき、その人が代わりに追悼ページを管理する仕組みがあります。これにより、誕生日通知や友達候補として表示されるといった機能は停止され、遺族に不要な悲しみを与えることを避けつつ、投稿や写真は残されるため、故人との思い出を共有することが可能になります。
Instagramでも同様に、家族や友人の申請によってアカウントが追悼状態に変更され、亡くなった人の投稿はそのまま閲覧できる形に変わります。ただし、ログインして新たな投稿や編集を行うことはできません。これは「削除」と大きく異なる点です。削除すればアカウント自体が消え、すべての情報が失われてしまいますが、追悼アカウントは「思い出を残す」という選択肢を提供します。
こうした制度は、遺族が「完全に消す」か「残す」かの二択で悩む負担を軽減し、デジタル遺品整理において柔軟な選択肢をもたらしています。
- 追悼アカウント=削除せず故人を偲ぶ場として残す仕組み
- Facebookは「追悼管理人」制度あり、通知停止・投稿閲覧可
- Instagramも申請で追悼化、編集不可だが思い出は残せる
- 削除は完全消去、追悼は保存と偲びを両立できる
主要SNSごとの対応まとめ
Facebook:追悼アカウントと追悼管理人制度
Facebookは追悼アカウント制度を早くから導入しており、故人のアカウントを削除せず残すことができます。生前に「追悼管理人」を指定しておくと、その人が代わりにプロフィールを管理し、追悼のメッセージを受け付けたり固定投稿を設定できます。誕生日通知や友達候補への表示は止まり、遺族に配慮した仕組みになっています。
Instagram:追悼アカウントか削除申請
Instagramでは、遺族や友人の申請によりアカウントを追悼モードにできます。これにより故人の写真や投稿は残りますが、ログインや編集はできず、閲覧専用となります。一方で削除申請も可能で、すべてのデータを消去できます。思い出を残すか消すか、遺族が選べる仕組みです。
LINE:相続人による解約手続き
LINEには追悼アカウント制度はなく、基本的には相続人が手続きを行い、アカウントを解約する形となります。未使用の残高(LINE Payやスタンプなど)がある場合は、条件に応じて払い戻しの申請が可能です。データやトーク履歴は引き継げず、プライバシー保護の観点から削除が基本です。
Twitter(X):遺族申請で削除のみ
Twitter(X)には追悼アカウント制度がなく、遺族が申請するとアカウントは削除されます。投稿内容を残す仕組みはなく、ログイン情報の開示も行われません。そのため思い出を保存したい場合は、事前にデータをダウンロードしておくなど生前準備が重要です。
Google/Apple:死亡後のアカウント管理機能
Googleには「アカウント無効化管理ツール」があり、生前に指定した相手がデータにアクセスできます。Appleも「デジタル遺産プログラム」を導入しており、死亡後に承認された相続人が写真やファイルにアクセス可能です。いずれも事前設定が重要で、準備の有無が大きな差となります。
遺品整理で直面する悩み
SNSを含むデジタル遺品は、遺品整理の中でも特に扱いが難しい分野です。まず大きな壁となるのが「思い出を残したい」という気持ちと、「個人情報を守りたい」という現実的な懸念のジレンマです。故人の投稿や写真は家族や友人にとってかけがえのない記録ですが、同時に住所や顔写真、交友関係といった個人情報が詰まっており、そのまま残すことで第三者に悪用されるリスクも抱えています。
さらに悩ましいのが、遺族間で意見が食い違うケースです。「削除して気持ちに区切りをつけたい」と考える人もいれば、「故人を偲ぶ場として残したい」と願う人もいます。どちらも正しい気持ちであるため、話し合いが平行線になることも少なくありません。そしてもう一つの大きな問題が、故人の意向が分からない場合です。生前に「削除してほしい」「残してほしい」と希望を伝えていないと、遺族が判断を迫られ、その責任や心理的負担は非常に大きなものとなります。こうした課題は、デジタル遺品整理が従来の遺品とは異なる難しさを持っていることを物語っています。
SNS遺品は思い出と個人情報保護の板挟み。遺族間の意見や故人の意向不明も悩み。