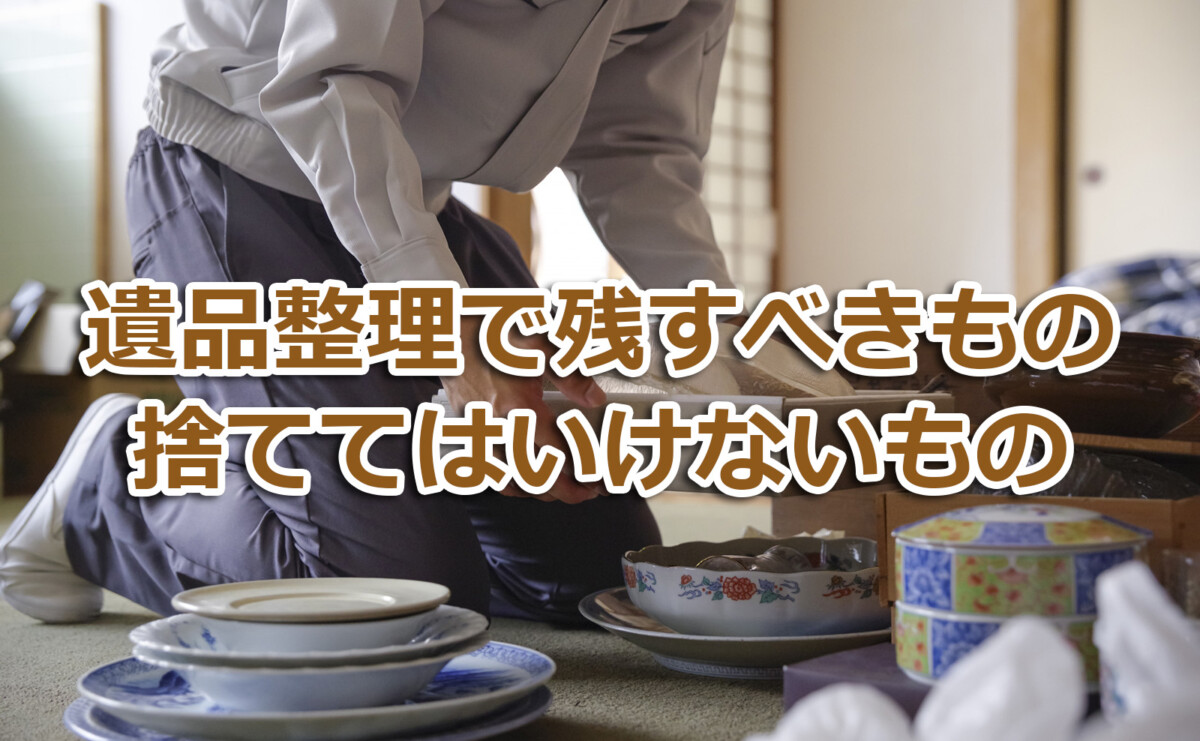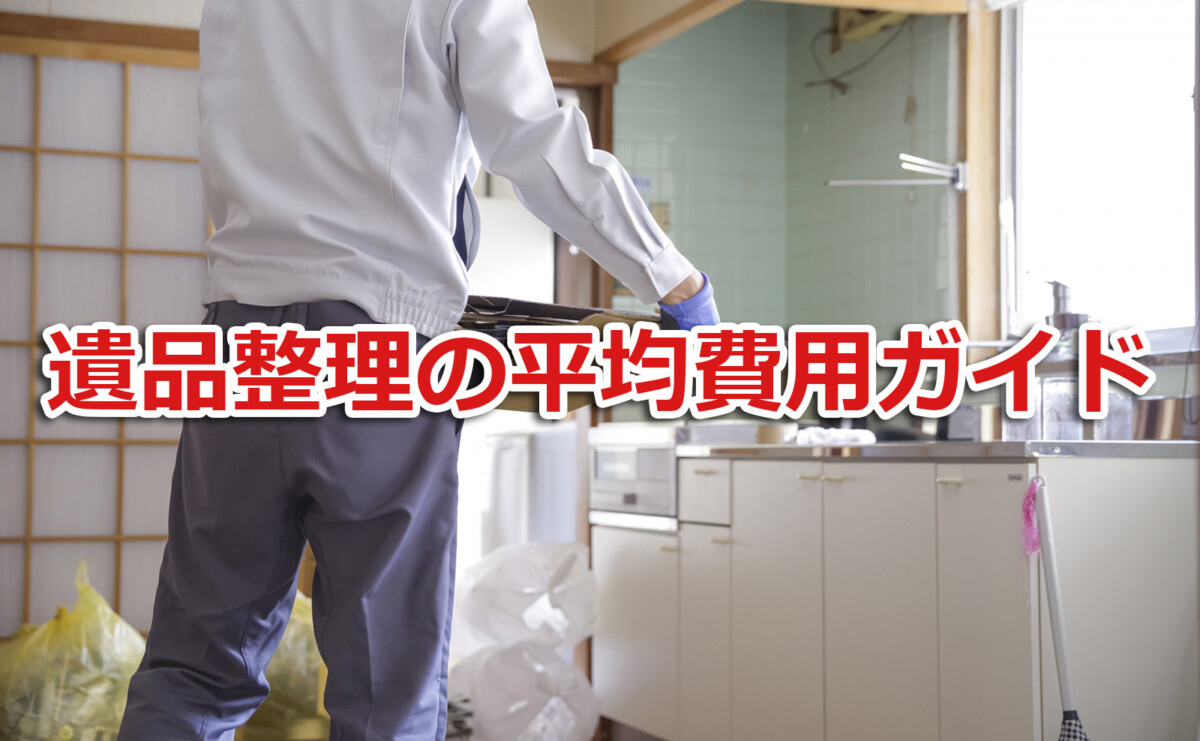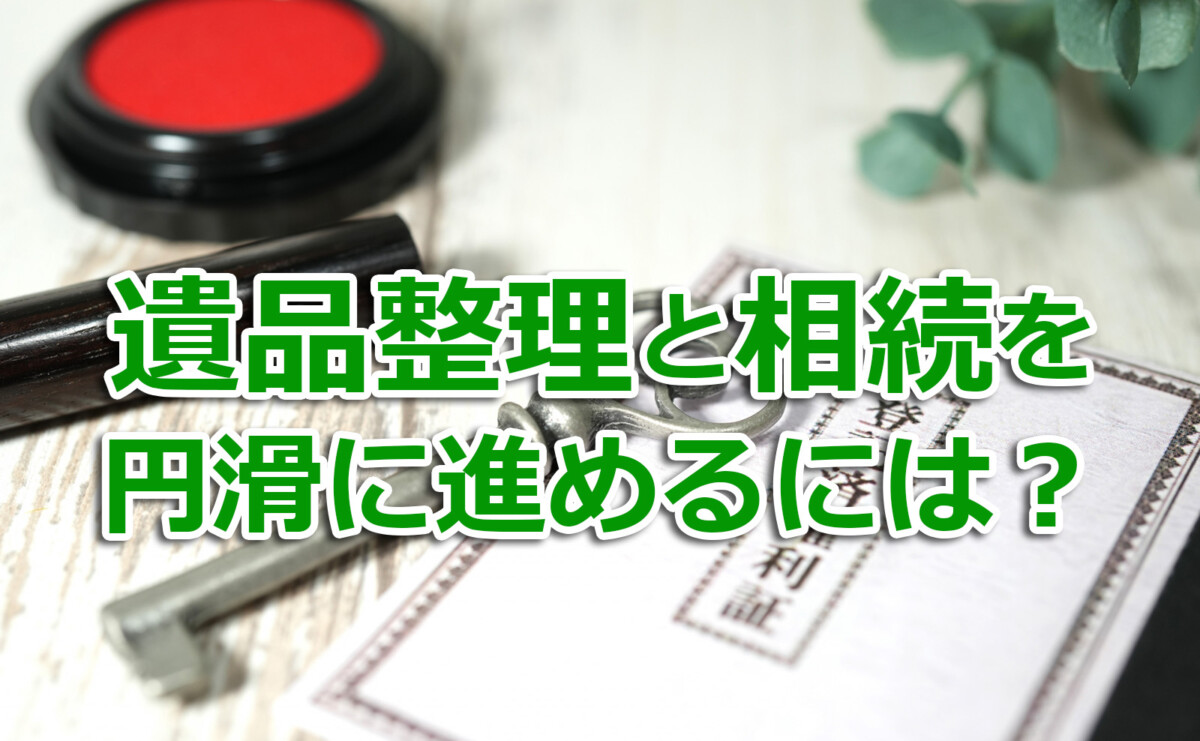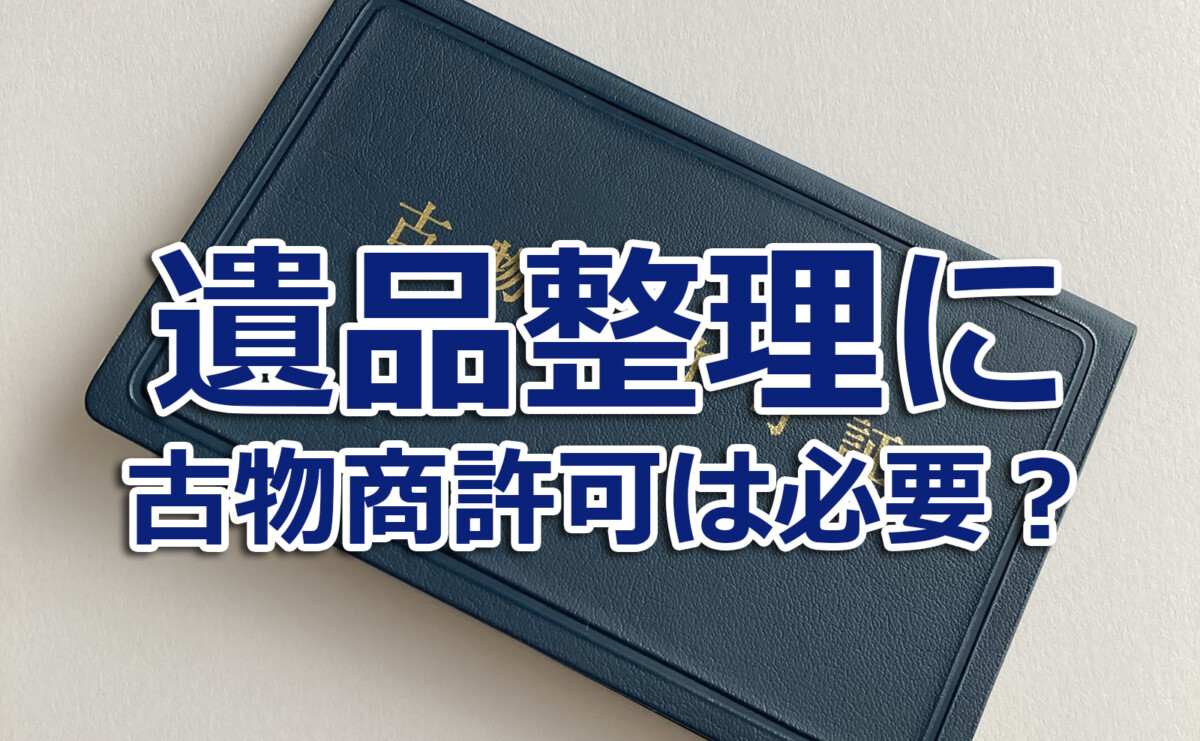遺品供養の対象となるもの
仏壇・位牌・神棚
仏壇や位牌、神棚といった宗教的な品は、故人を祀る大切な対象であり、処分に困る遺品の代表格です。単純に粗大ごみとして処分するのではなく、菩提寺や神社での供養や引き取りをお願いするのが一般的です。多くの場合は読経やお焚き上げとともに扱われ、故人への敬意を守りつつ丁寧に送り出せます。
写真・手紙・日記など思い出の品
写真や手紙、日記は故人の生涯や思い出を色濃く映す品であり、家族にとって感情的な重みが大きいものです。すべてを保管するのは難しいですが、そのまま処分するのも抵抗を感じるケースが多いでしょう。遺品供養を通じてまとめてお焚き上げすれば、「思い出を尊重しながら整理する」という形がとれ、気持ちの区切りを付けやすくなります。
人形・ぬいぐるみなど捨てにくいもの
人形やぬいぐるみは、子ども時代から長く共に過ごしたり、贈り物としての思い出が込められていたりするため、「魂が宿る」と感じて処分に迷う人が少なくありません。こうした品は、寺院や神社での人形供養に出すのが一般的です。感謝の気持ちを込めて供養することで、安心して手放すことができます。
その他「処分に迷うもの」
故人が愛用していた衣類や趣味の品、日用品など、一見すると普通のものでも家族にとっては思い出が強く残っている場合があります。「捨てるには忍びない」と感じる品は、遺品供養に含めることが可能です。供養を通じて気持ちに整理をつけることで、物理的な片付けと心のケアを同時に進められるのが大きな利点です。
遺品供養の流れ
まずは遺品の中から供養したいものを選び出します。写真や手紙、人形、仏壇や位牌など、処分に迷う品をまとめて仕分ける作業です。残すもの・処分するもの・供養に回すものを分けることで、心の準備を整えることにもつながります。段ボールや袋にまとめると、依頼時もスムーズです。
仕分けが済んだら、供養をお願いできる先を選びます。菩提寺や神社に持ち込む方法のほか、遺品整理業者や供養代行サービスに依頼するケースも増えています。近隣に頼れる寺院がない場合や大量にある場合は、業者に引き取りを依頼する方が現実的です。依頼先の信頼性を確認することが大切です。
実際の供養では、僧侶の読経や神職の祝詞、またはお焚き上げといった儀式が行われます。火を使って品を天に還すお焚き上げは「物の魂を鎮める」とされ、日本文化に根ざした方法です。こうした儀式を経ることで「捨てる」のではなく「送り出す」という感覚を得られ、遺族の心も整理されます。
供養が終わった遺品は、灰として処分されたり、一部は遺族に返却される場合もあります。たとえば写真や日記の一部を記念に残すよう依頼できるケースもあります。業者や寺院によって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。最後まで丁寧に見届けることで、より納得感のある供養になります。