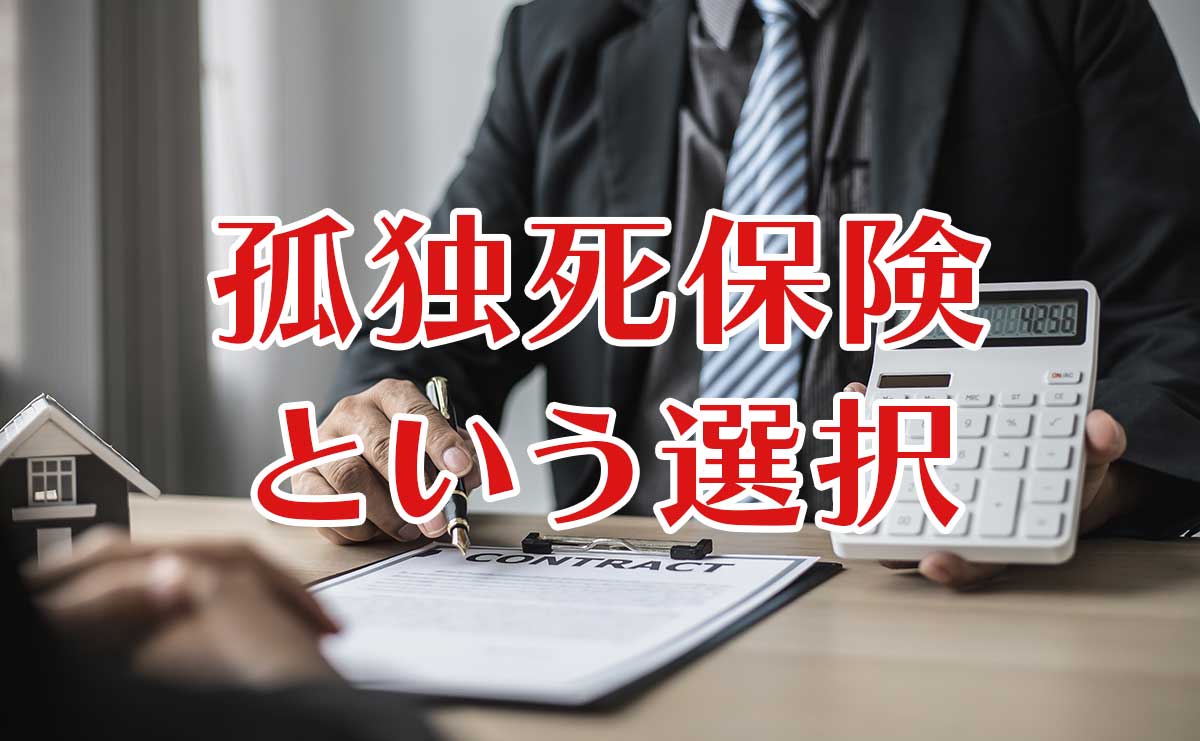はじめに:孤独死は他人事ではない
誰にも看取られず、自宅でひっそりと命を落とす──そんな「孤独死」と聞いて、どんな人を思い浮かべるでしょうか。おそらく多くの人が、高齢で一人暮らしをしている年配者の姿を想像するかもしれません。
しかし現実には、孤独死は高齢者だけの問題ではありません。
2025年2月に連載特集された朝日新聞の記事によれば、2023年に警察庁が初めて発表した孤独死の全国統計で、孤独死とされた人のうち、およそ4人に1人が15歳から64歳までの「現役世代」だったことが明らかになりました。これは、年金受給世代ではない私たちの世代にも、深刻な孤立のリスクが広がっていることを示しています。

その実態を象徴する出来事が、2022年、大阪で起きました。
朝日新聞の記事によれば、亡くなったのは42歳の男性。無職、独身で両親はすでに他界し、きょうだいもおらず、周囲との交流もほとんどありませんでした。彼が暮らしていた古い一軒家では、食べ物もなく、通帳の残高は百数十円、財布に現金もない状態だったといいます。
遺体が発見されたのは、死亡から1年以上が経過した後の2023年10月。すでに白骨化が進んでおり、事件性はないとされました。遺骨は今も引き取り手がないまま、丘の上にある納骨堂にひっそりと眠っているそうです。
朝日新聞の記事では、この男性が特別な事情を抱えていたわけではなく、誰にでも起こり得る「典型的な孤独死のケース」とされています。学歴があり、資格も取得し、就労経験もある。それでも、いつのまにか社会から見えにくい存在になり、誰にも気づかれず、助けも届かずに命を落としていったのです。
孤独死はもはや、高齢者特有の問題ではありません。支援の網が届きにくく、社会とのつながりを築く機会も少ない現役世代こそ、見過ごされやすいリスクを抱えているのです。
今回、朝日新聞が報じた実例や専門家の見解をもとに、現役世代の孤独死がなぜ増えているのか、どのような背景があるのか、そして私たちが今できることについて考えていきます。