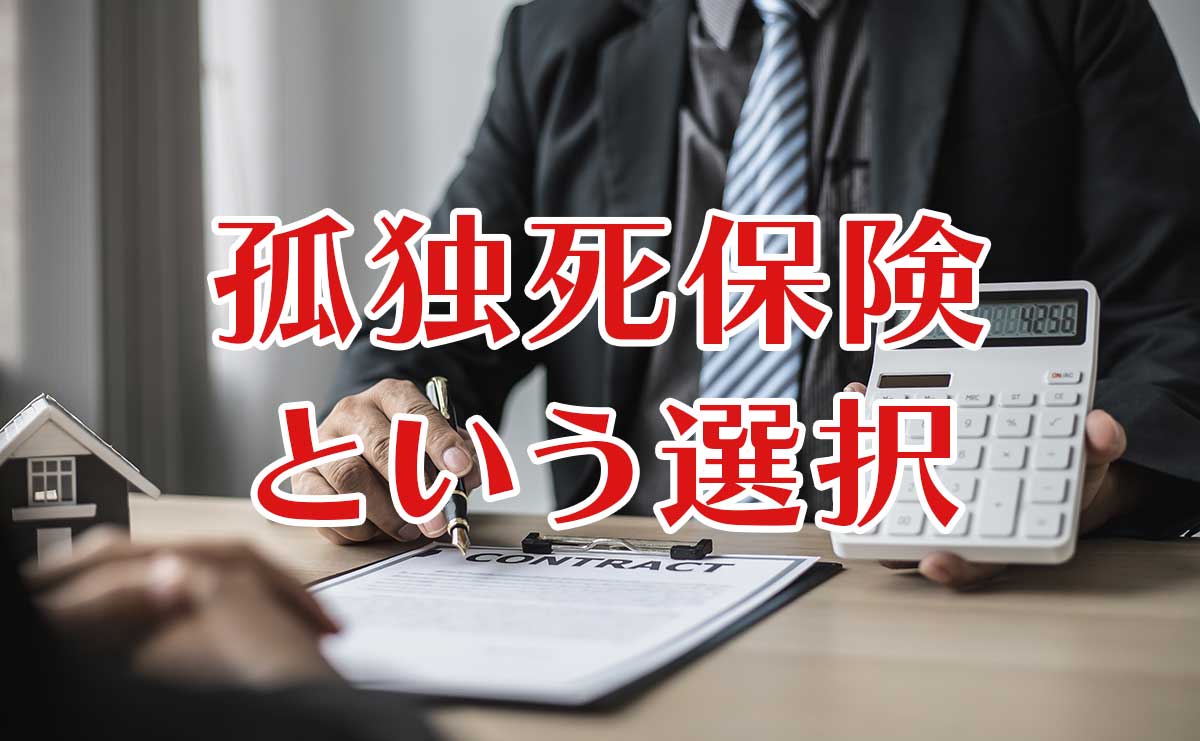孤独死を見越す44歳女性の選択
就職氷河期が残した「働く孤独」
朝日新聞の記事によれば、千葉県に暮らす44歳の女性・エミさん(仮名)は、大学卒業後の2003年に就職氷河期に直面し、希望していた出版社や大学事務職の採用には漏れ、40社以上の不採用通知を受けて就職活動を終えた。ようやくたどり着いたのは、非正規の図書館司書という道だった。20年以上、図書館で働き続けているが、月収は15万円弱。副業のライター収入を合わせても年収200万円には届かない。職場の人間関係は薄く、同僚と交わすのはあいさつや天気の話程度。家族とも疎遠になり、仕事以外の人間関係はほぼ皆無の生活が続いている。正社員としての安定も、家庭も持てなかったという事実が、彼女の孤独の根にある。
孤独死を避けるための「登録」
エミさんが孤独死を強く意識するようになったのは、大きな病気がきっかけだった。子宮筋腫が悪化し、手術を受けた後、約2週間、家で一人で過ごした。記事によれば、その間、自分が倒れても誰にも気づかれないのではないかという不安が頭をよぎったという。実際、日常的に会話を交わす相手も連絡を取る相手もおらず、LINEに届いた安否確認メッセージに「OK」とタップすることでしか、生きていることを誰かに伝える術がなかった。彼女は、東京都江戸川区のNPO法人「エンリッチ」が提供する見守りサービスに登録する。LINEでの簡易な安否確認システムは、彼女にとって「自分が死んだことを誰かに気づいてもらう」唯一の仕組みとなっている。
「死にたいわけじゃないけど、死ぬ覚悟はある」
エミさんは現在、毎月の収入の3分の1以上を家賃に充てながら生活し、月3,000円の貯金すら難しい状況だという。朝日新聞によれば、スーパーを何軒も回って安い食材を探し、「たまには牛肉を入れたい」というささやかな願いすら叶わない生活が続いている。そんな中で彼女が考えるようになったのは、「50代のうちに、誰にも迷惑をかけずに死にたい」という思いだった。自分が死ぬことよりも、死んだ後にペットが餓死することや、大家や近所に迷惑をかけることの方が怖い。とはいえ、「余裕が持てたなら、死にたくない」とも語る。彼女の言葉からは、死を望んでいるわけではなく、「孤立を選ばざるを得ない生活」の先に見える諦めがにじんでいる。
孤独は「未然に防げる病」か?
朝日新聞の記事では、エミさんのような人が増えていることを背景に、NPO代表が「孤独死は防ぐのが難しいが、人と人との関係をつくろうとする意識が大切だ」と語っている。エミさんも当初は「誰かと関わるのが怖い」と感じていたが、LINEでの安否確認という緩やかな関係性には、安心感を得ているようだ。スマホひとつでつながる見守りサービスは、現代に適した孤立対策として注目されている。とはいえ、問題の根は深い。非正規雇用の拡大、福祉制度からの距離、家族関係の希薄化といった社会的背景が、彼女のような人々を孤立へと追いやっている。「孤独=個人の問題」と片づけるのではなく、構造的課題として受け止める視点が求められている。

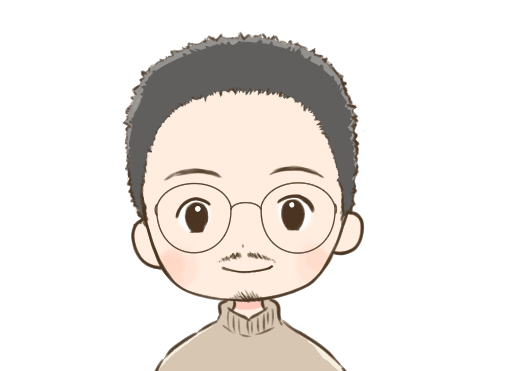 サイト管理人
サイト管理人エミさんの話から見えてくるのは、「死にたい」のではなく「生きている実感が持てない」日々を生きる現役世代の姿です。孤独死を防ぐためには、制度だけでなく「あなたは独りじゃない」と伝える社会のまなざしが必要です。
孤独死リスクの背景にある社会構造
「誰にも気づかれない孤立」という現役世代の現実
孤独死が「高齢者だけの問題ではない」と知ったとき、私は最初に戸惑いを感じました。実際、私たち現役世代は仕事をしていて、社会ともつながっているように思っていたからです。けれども、朝日新聞の記事によれば、2023年上半期に孤独死とされた人のうち、4人に1人が15歳〜64歳の「働き盛り世代」でした。
これは、ちょっとショックな数字です。家族がいない、友人が少ない、それだけではなく、「誰にも気づかれずに死ぬ」ことが、すぐそばにある現実だということです。
なぜ、現役世代で孤独死が起きるのか? 高齢者にはケアマネジャーやヘルパーなど日常的に見守る人がいますが、現役世代にはそうした目が届きません。朝日新聞が紹介した福祉学の斉藤教授の指摘によれば、数週間誰とも連絡が取れなくても「仕事が忙しいのかな」と思われて終わってしまうこともあるそうです。つまり、「誰も不自然に思わない孤立」 がこの世代の特徴なのです。
孤独は「個人の責任」ではなく社会の課題
もうひとつ、私が深く共感したのは「ライフコース型の孤立」という考え方です。誰かと別れて一人になったという「あとからの孤独」ではなく、最初から誰かと深くつながれなかった人の孤独。記事で紹介された42歳の男性や44歳のエミさんのように、若いころから家族・地域・職場すべてに緩やかに距離があり、そのまま誰にも頼れず歳を重ねてしまう。このタイプの孤独は、外から見ても気づかれにくく、深刻なまま放置されやすいのです。
そして、社会的背景にも目を向ける必要があります。非正規雇用の拡大、低収入、単身世帯の増加…。こうした構造的な要因が孤独を「個人の選択」に見せかけていますが、本当は誰もがこの流れの中に巻き込まれているのです。朝日新聞が伝えたように、「孤独は社会が生み出すリスク」であり、その有害性をもっと広く認識していく必要があると思います。
現代は「個人の自由」が尊重される時代です。でも、それと引き換えに「誰とも関わらずに生きられる社会」ができてしまったとも言えます。自分から声を上げなければ、誰にも助けてもらえない。だからこそ、「困ってる」と言える力=「受援力」が必要だと言われます。
でも私は思うのです。「困ってる」と言えるのは、安心して声を出せる場所があるときだけ。そこに誰かの「気づき」や「声かけ」があるかどうかで、人生の最終章がまるで違ってくるのではないでしょうか。
就職氷河期世代に見る「二極化」と構造的課題
氷河期世代が抱え続ける「見えない重し」
「自分は社会に必要ないのかもしれない」そんな思いを抱えながら働いている人が、どれだけいるでしょうか。
朝日新聞の記事によれば、孤独死を予感し、見守りサービスに登録したエミさん(44歳)も、まさにその一人です。
彼女は、いわゆる「就職氷河期世代」。バブル崩壊後の不況期に就職活動を経験した人たちです。記事によれば、40社以上から不採用の通知を受け、最終的に非正規の図書館司書として働き始めたエミさんの年収は200万円未満。副業をしても生活はぎりぎりで、老後どころか、明日の暮らしにも不安を抱えています。
東京大学の近藤教授が朝日新聞に語ったように、この世代の多くが安定した職につけなかったまま親の年金や支援に頼って生活しており、親が亡くなると一気に困窮するリスクを抱えています。そして困窮と孤立は、いつも背中合わせです。
この「見えない重し」は、履歴書に残るわけでもなく、本人の努力不足とも限らない。それでも、生活にのしかかり、将来への道をどんどん細くしていきます。
二極化する人生と次世代への影響
この氷河期世代の特徴は、「安定を得られた人」と「孤立に向かう人」との間に、大きな格差が生まれやすいことです。正規雇用に就き、家庭を築いた人たちと、非正規で孤立しがちな人たちとの二極化。エミさんのような立場の人は、パートナーを得ることも難しく、結果として老後に支え合える人間関係が構築できないまま、人生後半を迎えてしまいます。
しかもこれは、氷河期世代だけの話ではありません。朝日新聞によると、非正規雇用の割合は1989年には約19%だったのが、2023年には約37%に増加。つまり、安定した生活基盤を築けないまま社会に出る若者は今後も確実に増えるということです。
私自身、このデータを目にして、背筋が寒くなりました。もはや「特定の世代の問題」ではない。社会全体の仕組みのなかに、「孤独になりやすい構造」が埋め込まれているのです。
仕事が不安定、収入が少ない、家族がいない、頼れる人がいない…その全部がそろったとき、人は「孤独死のリスクゾーン」に入ってしまいます。そしてそのとき、周囲は「そんな状態になる前に助けを求めればよかったのに」と言うのです。
でも、助けを求めるにも「相手」が必要なんですよね。