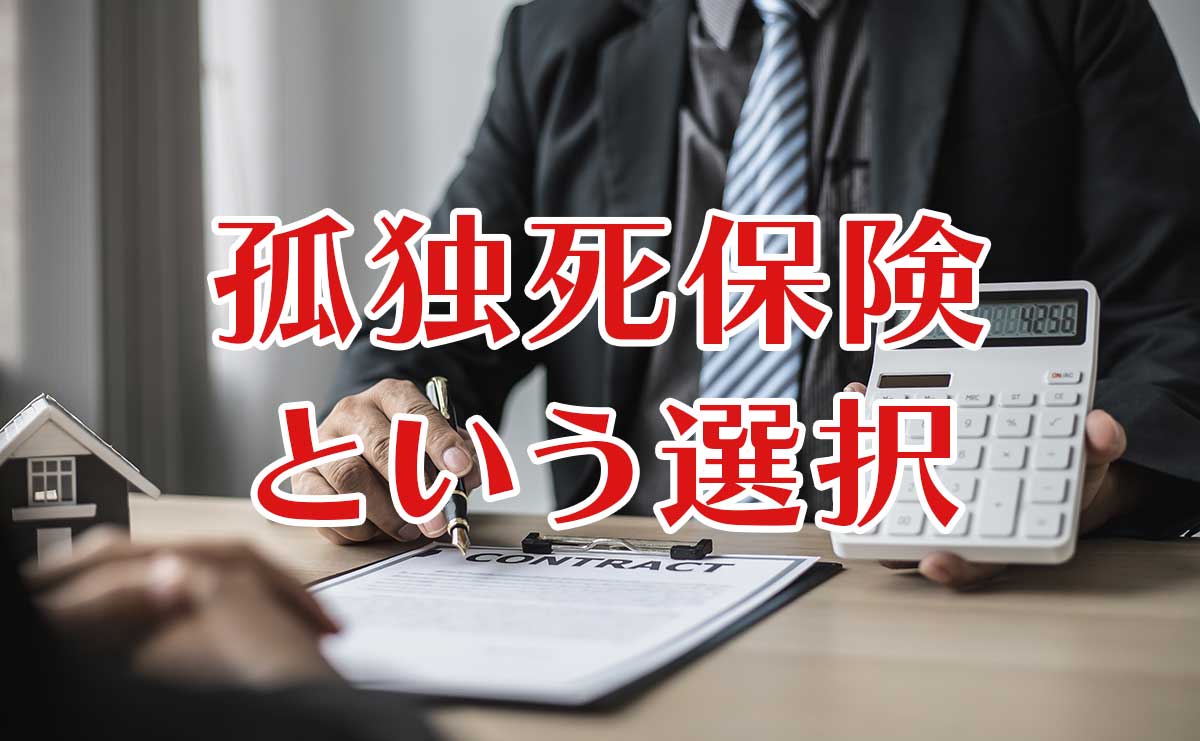支援の壁と「受援力」の課題
「困っている」と言えない現実
「本当は助けてほしいのに、誰にも言えない」。
これは、孤立する人たちの共通する心の声ではないでしょうか。
朝日新聞の記事でも、孤独死した男性や、見守りサービスに登録したエミさんのように、支援制度の存在自体は知っていたとしても、自分からそれに「つながる」ことができなかったという現実が描かれています。
人との関係を築くのが苦手だったり、過去に傷つく経験があったりすると、誰かに助けを求めること自体がハードルになります。しかも、現代は「自己責任」という言葉が社会に浸透しています。「苦しいのは自分の努力不足」「甘えていると思われたくない」。そうやって自分を責め、誰にも頼れなくなってしまうのです。
実際、支援の制度や窓口が整っていても、それが本当に「届いている」とは限りません。制度がある=支援が機能しているわけではない。そこには、支援を「受ける側」の力、つまり「受援力(じゅえんりょく)」という新たな課題があります。
支援は「気づき」から始まる
では、「受援力」が低い人に、どう支援を届けていけばいいのでしょうか。
その答えの一つが、朝日新聞で紹介されたNPO法人「エンリッチ」の取り組みにあると感じます。
エンリッチでは、LINEを使って安否確認をするシステムを提供しています。本人が「OK」をタップするだけで、元気でいることがわかる仕組み。逆に返答がないときには、スタッフがメールや電話で連絡し、最終的には訪問支援につなげる場合もあるそうです。
この「ゆるやかな見守り」は、まさに現代に適した支援のかたちだと思います。手を伸ばせない人に対して、支援のほうから「そっと近づく」。強引でもなく、放置でもない。そんな絶妙な距離感の支援が、これからの時代に求められているのではないでしょうか。
ただ、それでも支援が届かないケースはあります。地域や行政の支援制度を知らず、SNSやスマホにすら触れていない人もいる。だからこそ、支援は「制度の充実」だけではなく、「気づく仕組み」を整えることが重要なのです。
職場、学校、アパート、町内会どこにいても、「あれ、あの人最近見ないな」「元気かな」と思える関係性が、命を救う一歩になるかもしれません。
民間サービスと地域の可能性
テクノロジーで生まれる「つながりの代替」
「誰かとつながっていたい」けれど、直接会ったり電話をしたりするのはハードルが高い――そんな人にとって、テクノロジーは今や救いになり得ます。
朝日新聞の記事によれば、NPO法人「エンリッチ」が提供するLINEを活用した見守りサービスは、そうした人々の不安をそっと和らげています。仕組みはとてもシンプルで、LINEで「OK」をタップするだけ。返信がなければ、スタッフがメールや電話で確認し、それでも反応がなければ訪問を検討するというものです。
この「ゆるやかなつながり」が、孤独を感じる人の心のよりどころになっています。実際、登録者の中には「死んでも誰にも気づかれないと思っていたけれど、このサービスがあることで少し安心できた」と語る人もいるそうです。
特に印象的だったのは、LINEで「大丈夫?」と声をかけられたとき、エミさんが「誰かが気にかけてくれている」と感じたというエピソード。たった一言のメッセージが、孤独のどん底にいた彼女を少しだけ明るい場所に引き戻してくれたのです。
テクノロジーは、人の温もりを完全には代替できないかもしれません。でも、心の距離を埋めるための「きっかけ」にはなり得る。そんな希望を感じさせてくれる事例です。
地域と企業、そして「誰か」ができること
もちろん、見守りサービスだけで孤独死を完全に防げるわけではありません。もっと大切なのは、「気づく人」が地域や職場に一人でも増えることです。
朝日新聞の記事では、エンリッチの代表が「大切なのは、命に関心を持ち続けること」だと話しています。これがまさに本質だと感じました。孤独死を防ぐには、「制度」や「サービス」だけでは足りません。それらを使いこなせる土壌、つまり「人と人との関係」が必要なのです。
町内会や自治会、地域の高齢者見守り活動、あるいは会社の同僚やシェアハウスの仲間。どんな小さなコミュニティでも、「最近あの人見ないな」と気にかけることが、最初の一歩になります。
さらに、企業もできることがあります。福利厚生として見守りサービスへの加入支援を行ったり、従業員の孤立リスクをチェックする取り組みを進めたりと、間接的な支援でも十分意味があります。すべてを行政任せにせず、民間と地域が連携する仕組みがこれからますます重要になっていくでしょう。
そして、私たち一人ひとりにもできることがあります。それは、隣人や職場の仲間、SNSでつながっている誰かに「最近どう?」と声をかけてみること。それが、誰かの「最期を変える」かもしれません。
私たちにできること
「孤独死」と聞くと、どこか遠い世界の話に思えてしまうかもしれません。でも、実はとても身近な問題であり、誰の隣にも起こりうる現実です。
だからといって、私たち一人ひとりが何か大きな支援活動を始めなければならない、というわけではありません。朝日新聞の記事で紹介された事例から見えてきたのは、「ほんの小さな行動」こそが、大きな意味を持つということです。
たとえば、たまにしか会わない友人や親戚に「元気?」とLINEを送る。アパートの隣人に軽く会釈をする。町内会の掲示板を少し気にしてみる。職場の同僚の元気がなさそうだったら、「大丈夫?」と声をかける。そのひと声、そのひと手間が、誰かの孤立に歯止めをかける「きっかけ」になるかもしれません。
また、地域の見守り活動や自治会なども、実は孤独のサインをキャッチする大事な拠点です。大がかりなことをせずとも、「気にかける」「思い出す」だけで、私たちは孤独死を他人事から自分ごとに近づけることができるのです。
大切なのは、「支援する側」と「される側」に明確な線を引かないこと。「お互いさま」の気持ちで関わることで、人はつながりを感じやすくなります。支援も見守りも、もっと緩やかでいい。もっと自然体でいい。
その一歩が、明日誰かの命をつなぐかもしれません。
- LINEやSNSで、たまに連絡を取ってみる(元気?と一言だけでも)
- 近所の一人暮らしの人に軽い挨拶をする・話しかける
- 職場や学校で“ちょっとした変化”に気づく習慣を持つ
- 地域の見守り活動や防犯パトロールにゆるく参加してみる
- 民間の見守りサービスや支援制度の存在を知っておく
- 「困っている人がいたら頼っていい」と言葉で伝える
- 「あなたはひとりじゃない」と感じさせる空気をつくる
孤独死を「自己責任」で終わらせない社会へ
今回ご紹介した事例は、決して特別な人たちの話ではありません。働いていても、家族がいても、社会とつながっているつもりでも、人は簡単に孤立してしまう。
それが今の時代の怖さだと、改めて感じさせられました。
朝日新聞の記事が伝えたように、孤独死は「社会の側に要因がある」問題です。それを本人の弱さや運の悪さで片づけてしまっては、これからも同じことが繰り返されるでしょう。
大切なのは、社会全体が気づく力を持つこと。そして、「孤独死を出さない地域」をつくるのではなく、「孤独に気づける人がいる地域」を目指すことです。
たった一言の「大丈夫?」が、命を救うこともある。
私たちができることは、本当はそんなに難しいことではないのかもしれません。